目的:何故この本読もうとしたのか? 理由、目的、ゴールは?
本=魚(身と骨)
骨が大事 身は例等
【はじめに】 最初 頭
地頭力 読み込む力
5つの読み方
- 読解力 2.論理的思考力 3.要約力 4.客観的思考力 5.応用力
仮説作り(地図)と装丁読み(ライト)
パート1
・仮説作り(本の全体像と自分の現在地を知る) マクロな視点
※仮説作りで地図を作る訳だが、完璧な地図を作る必要はない
※本は全体として理解しないといけない
読めない原因は準備不足 → たった2つのことをすればどんな難解な文も読める
ようになる
それが、仮説作り(地図)と装丁読み(ライト)
本を読むという行為は暗い森の中に足を踏み入れる行為と一緒
地図とライトを持とう
仮説作りで地図(自分がその本から何を学ぶのかの目的)
装丁読みでライト(帯など)
装丁読み → 「一を聞いて十を知る」 手順
- タイトルからどういう情報を引き出せるか考える
- 引き出した情報を付箋に1枚ずつ書き出してみる
- 帯の両面を読み、得られる情報を1枚ずつ書き出してみる
- 著者のプロフィールを読みどういうバックグラウンドの人なのか
確認して得られる情報を付箋に1枚ずつ書き出してみる
たった3つのコツで表紙からたくさんの情報を引き出せる
- 分ける ②つなげる ③深読みする ※P40~43
付箋に残しておくことによって読解力を高める大きな効果がある
・残しておくことによって、後で見返した時に思い出しやすい
・手で書くことによって記憶に定着しやすい
・自分の言葉で書くことによって頭に定着しやすい
・1冊の本を読むのに時間がかかるから「装丁読み」しても情報量が多いから
忘れてしまう。一覧にしておけば見返し思い出しやすい
仮説作りの4ステップ(目標→現状→現状の順で設定)
- 「何故自分はその本を読むのか」の「目標」を付箋に書き出す
- 目次を見ながら①で設定した目標をどうやってその本で実現するのか
という「道筋」を考え付箋に書いた目標の下にまとめる
- 自分の現在どの立場にいるのかという「現状」を考え「道筋」の下にまとめる
- 実際に読み進めてみて、仮説と違うところが出たらその都度修正する
目標設定からすることによってより遠くまで行ける
東大生なら必ずやっている目標から逆算
目標を近くに設定してしまったら絶対にその先に行けない
本は遠くまで行く為のツール
人間は本を選ぶ時、自分と距離が遠くの方を選ぶ
・取材読み
「記者」になったつもりで読むと「記憶」にも「理解」も深まる
本は読むな 本の読者にならない
どういうことかと言うと、ただ本を読んでいる状態は
学校の授業を何もメモを取らずただただ来てる状態で
それではいくら東大生でも理解できない
本を読むという行為は相槌も打たずメモも取らず授業を聞くという行為と同じ
本を読める人は「記者」になったつもりで本を読む
「読者」 → 「記者」になる
記者は「相槌を打ち」ながら「メモと取り」ながら時には「質問を考え」ながら
著者の話を聞きます
記者になる姿勢
東大生は皆姿勢が良い
寝そべって本を読んだり、椅子に深く腰かけて本を読んだりすると
ただ、文字を追ったり読み飛ばしたりしてしまう
記者は前のめりに取材するので、本を読む時は本を大きく開きできるだけ
本に近づき読む
記者になることの2つのメリット
・感情を入れて読めるようになるので、新書やビジネス書などの知識を得る目的
の本で「へぇ そうなんだ」と読んでしまいがちな本もたくさんのことを想起し
ながら読むことが可能です。
ただの事実に感情を加えることによって、色を付けられ文書を理解しやすくなる
・文書の流れが追いやすくなる
感情を理解すれば、その次からの流れが理解できるようになる
質問読みで「情報」も「知識」に変える
質問読みとは?
情報を鵜呑みにしない
例題:西岡君はかっこいいですか? 回答:かっこいい。会ってみたい。興味ない
等の回答をした人は、情報を鵜呑みにしている可能性があり読解力がない人
逆に、この質問に疑問(西岡君ってどこの誰やねん)を持てた人は読解力がある人。
「情報」は「知識」にして初めて生きてくる
「情報」を得るだけなら、スマホや電子書籍の方が得やすいですが、本がまだ残って
いるのか?本は「知識」を得られるからです。
「質問読み」の方法
- 読み進めていく中で、質問になる部分を探す
※著者が「何故、この傾向があるのでしょう?」等投げかけていたらその
「問い」を質問にすると「知識」になります。
- 質問が見つかったらそのページに付箋を貼る
- 質問の回答が出てきたらそこに付箋を貼る
「重要な質問」を考える3つの視点
- 著者が最初に提示してるもの
著者が最初に投げかけている問
- 「質問」への回答が複数ありそうな質問
- 議論が分かれそうなものに対する質問
質問読みの効果とは?
良い質問とは著者にとっての良い質問でありそれが良い読者になる
池上彰さんが良く言う「良い質問ですね」は質問の質自体が良いと言う
意味合いではない。
弁論のテクニックとしてわざと突っ込んで欲しい穴を作っておくというのがある。
良い質問だろうが悪い質問だろうが重要なのは質問を考えてみるということ
追求読みで「自分で考える力」を鍛える
「疑わしいこと」に疑問を持ち、自分で調べるのが「追求読み」
「質問」と「疑問」は違う
「質問」を考えると「読解力」が「疑問」を考えると「思考力」が鍛えられる
「追求読み」の方法
- 1回読んだ本や章を選ぶ
- その本を、「本当にそうか?」と常に疑問を抱きつつ読んでいく
- 読み進めていく中で、抱いた疑問が解消されるか、残り続けるを見極める
- 本や章を読み終わるまで残り続けた疑問をノートに写し、調べてみる
ここでオススメ
1冊の本を読む時など、疑問を多く持ちすぎると忘れるので疑問に付箋をつけ
解消したら取って、疑問を持ったらまたつけて、を繰り返す。
最後に残った疑問はまとめやすい。
追求読みの注意点
一度読んだ本は、最初に読んだときにはスルーした部分を、前はスルーして
しまったけど、実際のところどうなんだろう?とか、新たに疑問を持ちやすい
自分で考えることを意識的に続ければ自分で考える力を鍛えられる
調べるのは最後まで残った疑問だけでいい。
「追求読み」は結局「深い知識」につながる
「他人からの回答」は自分の物ではない分頭に入ってこない
「追求読み」は結局「自分で考える」からより深い知識が得られる
・整理読み(どうすれば美味しく魚を食べられるか?その為の読書)
(本を読むと言う行為が整理読みであり魚を食べる行為)
整理読みとは?
本を読む上で一番気をつけることは「分かった気に」ならないこと
その本で著者が本当に何を伝えたかったのか、一言で伝えられなければ
分かった気になっているのと同じ
要約できるかどうか
どんな見方にもミクロの見方とマクロの見方があり
要するに何なのか?が理解できていない状態は全体(マクロ)が理解出来ない状態
「一言で言い表せられるか出来るか出来ないか」が文章を分かっているか
分かっていないかの分岐点なのです
短くまとめられている=ちゃんと理解している
要するに、少ない文字数で自分の考えや人の意見をまとめられないといのは
ちゃんと理解していないということ
わかった気になるのは?
単純に、本が長いから
本は「魚」ある(骨・身)
何が一番言いたいことなのか?
本を書く側は、本は魚
読む側は、本は森
著者の「結論」「言いたいこと」が冒頭にくることが多い
どんな文章もこの様に作られている
「著者」が伝えたいのは「骨」であって「身」ではない
「本」はどうしても分量が身が多くなってしまいがち
そこで、「頭」と「尾尻」(おじり)
本は「魚」であり、4「身」と「骨」があり
「骨」は言いたいこと、「身」はそれを補強すること
整理する=骨と身の分離
整理読みとは、「著書の言いたいこと」と「それを補強する言説」を切り分ける
整理が出来はじめて、自分の意見を持つことができる
要約読み(整理テクニック1)で「一言でシンプルに表現できる」ようになる
ちゃんと骨が残っているのかどうかを確認するために必要なのが「要約」
「要するに何?」を短文で示せる、著者が「本当に言いたいこと」が現れて
いるのはどの文なのか?をチェックしつつ読み進めるか?
要約読みのやり方
- 1節分・1章分を読み、その中から「要約的な一文」を探す
- その一文を踏まえて、ノートに30字以内で1章・1節の「まとめ」を書く
- 「まとめ」を踏まえて、章全体・本全体のまとめを140字以内で作る
※140字というのはツイッターの文字制限数なのでツイッターを活用
ワンポイント
誰が読んでもわかりやすく書く。中学生が読んでも、その本を読んだことが無い
人でもわかるように書く。
要約的な一文の探し方
- 最初と最後の近くの文
- 「しかし」の文の後
- [~なのではないでしょうか?]文
- 「装丁読み」で見つけた内容が書かれた文
推測読み(整理テクニック2)
「次の展開」を予測できるようになる
「骨」さえわかれば「次に何が来るか」推測できる
「自分の意見」は「骨」と「身」を分離してから
著者が言いたいことが何なのか理解してはじめて、自分の意見が作れる
推測読みのやり方
- 新しい節・章を読む前に、今までの「要約読み」でまとめた要約文を見直す
- 次の節・章のタイトルを確認し、「次の節・章には何が書いてあるのか」を
考えてノートにまとめてみる
- その章でも「要約読み」を行い、「推測読み」がどれくらい正しかった確認する
「推測」の4パターン
- 例示
- 比較
- 追加
- 抽象化・一般化
著者が本当に言いたいことを追うのが推測で「骨」になる主張が何なのかを
見極めながら推測するのが「推測読み」
「要約読み」「推測読み」を同時並行すれば常に「整理」しながら読める様になる
・検証読み(辞書で調べるのも、簡単な本でわかったも検証読みで考える力つく)
検証読みで「多面的なモノの見方」を身につける
―東大生はカバンの中に「2冊の本」を入れているー
本は2冊同時に読むことによって効果が何倍にもなる!
まず、1冊ずつ読んではいけない。
多くの人は、1冊読み終わってから次の本を読む
実は、1冊の本からより多くのインプットが得られるのは
「同時並行で複数の本を読む」読み方なんです=検証読み
意見の偏りを避けられる
人の数だけ正しさがあって、人の数だけ意見がある
主体的な読書が出来るようになる(受け身の読書を避けられる)
科学的にも理にかなっている
同時に読むからこそ効果がある
1冊読んでから次の本を読むのはほとんど忘れている
エビングハウスの忘却曲線
人間は20分後には 42%忘れている
1時間後には 54%
1日後には 74%
1周間後には 79%
次の本読むころには7割以上を忘れている状態(1冊読むのに1日~7日)
「長期記憶」を作るには、「検証読み」が最適
何度も何度も復習するうちにこの「忘却曲線」の減り具合のスピード
が緩やかになっていく
脳科学的に記憶というのは2つに分類される
「短期記憶」「長期記憶」 → 決めるのは「海馬」
「海馬」が長期記憶と短期記憶を判断するのは
何度も見ている情報を「重要」だと判断する
考える力は東大も求め力で、最近の人は指示待ち人間が多く
イエスマンが増えてしまった原因はこの考える力が無い為
受動的(考えないで本を読む・テレビをただなんとなく観る)
な行為より能動的に本を読もう
パラレル読みで「別の切り口から考える」を身につける
どうやって2冊選ぶのか(共通す部分が多い似てる2冊)
パラレル読みの手順
- 関連性のある2冊を選ぶ
- 選んだ2冊をなるべく同じスピードで読み進めていく
- 2冊にあhどんな共通点、どんな違いがあるのか考えてみる
- 思いついた共通点と相違点を、付箋に書いて貼っていく
- 読み終わった後に相違点の付箋を見直して「どうして両者の主張が食い違っているのだろう?「何で意見が分かれるのだろう?」と
一つひとつ「検証」していく
自分の中で一つの「結論」だそうと考えてみる行為が大事で意味がある
共通点も相違点も発見しやすい2冊の例
- ポジティブな目線で見る本とネガティティブな目線で見る本
- 目線が違う本
- 人物・地域・出来事など、着眼点が違う本
- ミクロな視点から見る本とマクロな視点から見る本
- 読者ターゲットが違う本
- 著者の立場が違う本
「パラレル読み」で「共通点」を探し、「相違点」を見つけ
「相違点の理由」を考えれば、自然と「多面的な思考力」が身につく!
クロス読みで「思考力」「幅広い視点」を身につける
クロス読みとは
意見と意見が交差するポイントを見つける読み方
クロス読みの手順
- 複数の本を読んでいく中で議論が分かれる点、交差ポイントを探す
- 見つけた交差ポイントを別の本を参照して検証してみる
- 交差ポイントをノートに書きその交差ポイントに対するさまざまな意見をまとめる
・議論読み(本と議論する・アウトプット)
読みっぱなしは効果半減
本とは会話する
アウトプットですべて変わる
アウトプットとインプットはどんな物事にも当てはまる
読書をする場合でも当てはまる、著者に質問を投げかけるのもアウトプット
でそれをすることによって知識も定着していくし読解力も向上する
読んだ内容や鑑賞した内容はまだ「自分の言葉」になってない(インプット)
「アウトプット」前提で読むからこそ「読んだ内容を後からアウトプットしよう」
という意識を働かせながら「インプット」することもできる
読んだ本をそのままにしてしまうのはインプットだけ
「インプット」を自分の知識にするのが「アウトプット」
「アウトプット」しようと意識するのが「インプット」の質が高くなる
この本の全てが「本との会話の仕方」を説明するものだった
STEP1~STEP4のアウトプットを踏まえて本の議論をすることが議論読み
以上、読み終わった後の「アウトプット」は以下の3点「議論読みのテクニック」
- STEP1で立てた仮説の答え合わせ
- STEP3での要約 アウトプット要約
- 感想・意見 自分なりの結論
パート2
読むべき本の探し方
・売れている本 ベストセラー
・信頼できる人からの紹介
・古典
今年のマイテーマを決める
【終わりに】 最後 尻尾
何気ない本の1説が誰かに刺さることがある。
なんでも無い本の1ページによって人生が変わるという人もいる。
本の良し悪しは、読みてによって変わる。
変わらなければならないのは、読み手の方目的:何故この本読もうとしたのか? 理由、目的、ゴールは?
本=魚(身と骨)
骨が大事 身は例等
【はじめに】 最初 頭
地頭力 読み込む力
5つの読み方
- 読解力 2.論理的思考力 3.要約力 4.客観的思考力 5.応用力
仮説作り(地図)と装丁読み(ライト)
パート1
・仮説作り(本の全体像と自分の現在地を知る) マクロな視点
※仮説作りで地図を作る訳だが、完璧な地図を作る必要はない
※本は全体として理解しないといけない
読めない原因は準備不足 → たった2つのことをすればどんな難解な文も読める
ようになる
それが、仮説作り(地図)と装丁読み(ライト)
本を読むという行為は暗い森の中に足を踏み入れる行為と一緒
地図とライトを持とう
仮説作りで地図(自分がその本から何を学ぶのかの目的)
装丁読みでライト(帯など)
装丁読み → 「一を聞いて十を知る」 手順
- タイトルからどういう情報を引き出せるか考える
- 引き出した情報を付箋に1枚ずつ書き出してみる
- 帯の両面を読み、得られる情報を1枚ずつ書き出してみる
- 著者のプロフィールを読みどういうバックグラウンドの人なのか
確認して得られる情報を付箋に1枚ずつ書き出してみる
たった3つのコツで表紙からたくさんの情報を引き出せる
- 分ける ②つなげる ③深読みする ※P40~43
付箋に残しておくことによって読解力を高める大きな効果がある
・残しておくことによって、後で見返した時に思い出しやすい
・手で書くことによって記憶に定着しやすい
・自分の言葉で書くことによって頭に定着しやすい
・1冊の本を読むのに時間がかかるから「装丁読み」しても情報量が多いから
忘れてしまう。一覧にしておけば見返し思い出しやすい
仮説作りの4ステップ(目標→現状→現状の順で設定)
- 「何故自分はその本を読むのか」の「目標」を付箋に書き出す
- 目次を見ながら①で設定した目標をどうやってその本で実現するのか
という「道筋」を考え付箋に書いた目標の下にまとめる
- 自分の現在どの立場にいるのかという「現状」を考え「道筋」の下にまとめる
- 実際に読み進めてみて、仮説と違うところが出たらその都度修正する
目標設定からすることによってより遠くまで行ける
東大生なら必ずやっている目標から逆算
目標を近くに設定してしまったら絶対にその先に行けない
本は遠くまで行く為のツール
人間は本を選ぶ時、自分と距離が遠くの方を選ぶ
・取材読み
「記者」になったつもりで読むと「記憶」にも「理解」も深まる
本は読むな 本の読者にならない
どういうことかと言うと、ただ本を読んでいる状態は
学校の授業を何もメモを取らずただただ来てる状態で
それではいくら東大生でも理解できない
本を読むという行為は相槌も打たずメモも取らず授業を聞くという行為と同じ
本を読める人は「記者」になったつもりで本を読む
「読者」 → 「記者」になる
記者は「相槌を打ち」ながら「メモと取り」ながら時には「質問を考え」ながら
著者の話を聞きます
記者になる姿勢
東大生は皆姿勢が良い
寝そべって本を読んだり、椅子に深く腰かけて本を読んだりすると
ただ、文字を追ったり読み飛ばしたりしてしまう
記者は前のめりに取材するので、本を読む時は本を大きく開きできるだけ
本に近づき読む
記者になることの2つのメリット
・感情を入れて読めるようになるので、新書やビジネス書などの知識を得る目的
の本で「へぇ そうなんだ」と読んでしまいがちな本もたくさんのことを想起し
ながら読むことが可能です。
ただの事実に感情を加えることによって、色を付けられ文書を理解しやすくなる
・文書の流れが追いやすくなる
感情を理解すれば、その次からの流れが理解できるようになる
質問読みで「情報」も「知識」に変える
質問読みとは?
情報を鵜呑みにしない
例題:西岡君はかっこいいですか? 回答:かっこいい。会ってみたい。興味ない
等の回答をした人は、情報を鵜呑みにしている可能性があり読解力がない人
逆に、この質問に疑問(西岡君ってどこの誰やねん)を持てた人は読解力がある人。
「情報」は「知識」にして初めて生きてくる
「情報」を得るだけなら、スマホや電子書籍の方が得やすいですが、本がまだ残って
いるのか?本は「知識」を得られるからです。
「質問読み」の方法
- 読み進めていく中で、質問になる部分を探す
※著者が「何故、この傾向があるのでしょう?」等投げかけていたらその
「問い」を質問にすると「知識」になります。
- 質問が見つかったらそのページに付箋を貼る
- 質問の回答が出てきたらそこに付箋を貼る
「重要な質問」を考える3つの視点
- 著者が最初に提示してるもの
著者が最初に投げかけている問
- 「質問」への回答が複数ありそうな質問
- 議論が分かれそうなものに対する質問
質問読みの効果とは?
良い質問とは著者にとっての良い質問でありそれが良い読者になる
池上彰さんが良く言う「良い質問ですね」は質問の質自体が良いと言う
意味合いではない。
弁論のテクニックとしてわざと突っ込んで欲しい穴を作っておくというのがある。
良い質問だろうが悪い質問だろうが重要なのは質問を考えてみるということ
追求読みで「自分で考える力」を鍛える
「疑わしいこと」に疑問を持ち、自分で調べるのが「追求読み」
「質問」と「疑問」は違う
「質問」を考えると「読解力」が「疑問」を考えると「思考力」が鍛えられる
「追求読み」の方法
- 1回読んだ本や章を選ぶ
- その本を、「本当にそうか?」と常に疑問を抱きつつ読んでいく
- 読み進めていく中で、抱いた疑問が解消されるか、残り続けるを見極める
- 本や章を読み終わるまで残り続けた疑問をノートに写し、調べてみる
ここでオススメ
1冊の本を読む時など、疑問を多く持ちすぎると忘れるので疑問に付箋をつけ
解消したら取って、疑問を持ったらまたつけて、を繰り返す。
最後に残った疑問はまとめやすい。
追求読みの注意点
一度読んだ本は、最初に読んだときにはスルーした部分を、前はスルーして
しまったけど、実際のところどうなんだろう?とか、新たに疑問を持ちやすい
自分で考えることを意識的に続ければ自分で考える力を鍛えられる
調べるのは最後まで残った疑問だけでいい。
「追求読み」は結局「深い知識」につながる
「他人からの回答」は自分の物ではない分頭に入ってこない
「追求読み」は結局「自分で考える」からより深い知識が得られる
・整理読み(どうすれば美味しく魚を食べられるか?その為の読書)
(本を読むと言う行為が整理読みであり魚を食べる行為)
整理読みとは?
本を読む上で一番気をつけることは「分かった気に」ならないこと
その本で著者が本当に何を伝えたかったのか、一言で伝えられなければ
分かった気になっているのと同じ
要約できるかどうか
どんな見方にもミクロの見方とマクロの見方があり
要するに何なのか?が理解できていない状態は全体(マクロ)が理解出来ない状態
「一言で言い表せられるか出来るか出来ないか」が文章を分かっているか
分かっていないかの分岐点なのです
短くまとめられている=ちゃんと理解している
要するに、少ない文字数で自分の考えや人の意見をまとめられないといのは
ちゃんと理解していないということ
わかった気になるのは?
単純に、本が長いから
本は「魚」ある(骨・身)
何が一番言いたいことなのか?
本を書く側は、本は魚
読む側は、本は森
著者の「結論」「言いたいこと」が冒頭にくることが多い
どんな文章もこの様に作られている
「著者」が伝えたいのは「骨」であって「身」ではない
「本」はどうしても分量が身が多くなってしまいがち
そこで、「頭」と「尾尻」(おじり)
本は「魚」であり、4「身」と「骨」があり
「骨」は言いたいこと、「身」はそれを補強すること
整理する=骨と身の分離
整理読みとは、「著書の言いたいこと」と「それを補強する言説」を切り分ける
整理が出来はじめて、自分の意見を持つことができる
要約読み(整理テクニック1)で「一言でシンプルに表現できる」ようになる
ちゃんと骨が残っているのかどうかを確認するために必要なのが「要約」
「要するに何?」を短文で示せる、著者が「本当に言いたいこと」が現れて
いるのはどの文なのか?をチェックしつつ読み進めるか?
要約読みのやり方
- 1節分・1章分を読み、その中から「要約的な一文」を探す
- その一文を踏まえて、ノートに30字以内で1章・1節の「まとめ」を書く
- 「まとめ」を踏まえて、章全体・本全体のまとめを140字以内で作る
※140字というのはツイッターの文字制限数なのでツイッターを活用
ワンポイント
誰が読んでもわかりやすく書く。中学生が読んでも、その本を読んだことが無い
人でもわかるように書く。
要約的な一文の探し方
- 最初と最後の近くの文
- 「しかし」の文の後
- [~なのではないでしょうか?]文
- 「装丁読み」で見つけた内容が書かれた文
推測読み(整理テクニック2)
「次の展開」を予測できるようになる
「骨」さえわかれば「次に何が来るか」推測できる
「自分の意見」は「骨」と「身」を分離してから
著者が言いたいことが何なのか理解してはじめて、自分の意見が作れる
推測読みのやり方
- 新しい節・章を読む前に、今までの「要約読み」でまとめた要約文を見直す
- 次の節・章のタイトルを確認し、「次の節・章には何が書いてあるのか」を
考えてノートにまとめてみる
- その章でも「要約読み」を行い、「推測読み」がどれくらい正しかった確認する
「推測」の4パターン
- 例示
- 比較
- 追加
- 抽象化・一般化
著者が本当に言いたいことを追うのが推測で「骨」になる主張が何なのかを
見極めながら推測するのが「推測読み」
「要約読み」「推測読み」を同時並行すれば常に「整理」しながら読める様になる
・検証読み(辞書で調べるのも、簡単な本でわかったも検証読みで考える力つく)
検証読みで「多面的なモノの見方」を身につける
―東大生はカバンの中に「2冊の本」を入れているー
本は2冊同時に読むことによって効果が何倍にもなる!
まず、1冊ずつ読んではいけない。
多くの人は、1冊読み終わってから次の本を読む
実は、1冊の本からより多くのインプットが得られるのは
「同時並行で複数の本を読む」読み方なんです=検証読み
意見の偏りを避けられる
人の数だけ正しさがあって、人の数だけ意見がある
主体的な読書が出来るようになる(受け身の読書を避けられる)
科学的にも理にかなっている
同時に読むからこそ効果がある
1冊読んでから次の本を読むのはほとんど忘れている
エビングハウスの忘却曲線
人間は20分後には 42%忘れている
1時間後には 54%
1日後には 74%
1周間後には 79%
次の本読むころには7割以上を忘れている状態(1冊読むのに1日~7日)
「長期記憶」を作るには、「検証読み」が最適
何度も何度も復習するうちにこの「忘却曲線」の減り具合のスピード
が緩やかになっていく
脳科学的に記憶というのは2つに分類される
「短期記憶」「長期記憶」 → 決めるのは「海馬」
「海馬」が長期記憶と短期記憶を判断するのは
何度も見ている情報を「重要」だと判断する
考える力は東大も求め力で、最近の人は指示待ち人間が多く
イエスマンが増えてしまった原因はこの考える力が無い為
受動的(考えないで本を読む・テレビをただなんとなく観る)
な行為より能動的に本を読もう
パラレル読みで「別の切り口から考える」を身につける
どうやって2冊選ぶのか(共通す部分が多い似てる2冊)
パラレル読みの手順
- 関連性のある2冊を選ぶ
- 選んだ2冊をなるべく同じスピードで読み進めていく
- 2冊にあhどんな共通点、どんな違いがあるのか考えてみる
- 思いついた共通点と相違点を、付箋に書いて貼っていく
- 読み終わった後に相違点の付箋を見直して「どうして両者の主張が食い違っているのだろう?「何で意見が分かれるのだろう?」と
一つひとつ「検証」していく
自分の中で一つの「結論」だそうと考えてみる行為が大事で意味がある
共通点も相違点も発見しやすい2冊の例
- ポジティブな目線で見る本とネガティティブな目線で見る本
- 目線が違う本
- 人物・地域・出来事など、着眼点が違う本
- ミクロな視点から見る本とマクロな視点から見る本
- 読者ターゲットが違う本
- 著者の立場が違う本
「パラレル読み」で「共通点」を探し、「相違点」を見つけ
「相違点の理由」を考えれば、自然と「多面的な思考力」が身につく!
クロス読みで「思考力」「幅広い視点」を身につける
クロス読みとは
意見と意見が交差するポイントを見つける読み方
クロス読みの手順
- 複数の本を読んでいく中で議論が分かれる点、交差ポイントを探す
- 見つけた交差ポイントを別の本を参照して検証してみる
- 交差ポイントをノートに書きその交差ポイントに対するさまざまな意見をまとめる
・議論読み(本と議論する・アウトプット)
読みっぱなしは効果半減
本とは会話する
アウトプットですべて変わる
アウトプットとインプットはどんな物事にも当てはまる
読書をする場合でも当てはまる、著者に質問を投げかけるのもアウトプット
でそれをすることによって知識も定着していくし読解力も向上する
読んだ内容や鑑賞した内容はまだ「自分の言葉」になってない(インプット)
「アウトプット」前提で読むからこそ「読んだ内容を後からアウトプットしよう」
という意識を働かせながら「インプット」することもできる
読んだ本をそのままにしてしまうのはインプットだけ
「インプット」を自分の知識にするのが「アウトプット」
「アウトプット」しようと意識するのが「インプット」の質が高くなる
この本の全てが「本との会話の仕方」を説明するものだった
STEP1~STEP4のアウトプットを踏まえて本の議論をすることが議論読み
以上、読み終わった後の「アウトプット」は以下の3点「議論読みのテクニック」
- STEP1で立てた仮説の答え合わせ
- STEP3での要約 アウトプット要約
- 感想・意見 自分なりの結論
パート2
読むべき本の探し方
・売れている本 ベストセラー
・信頼できる人からの紹介
・古典
今年のマイテーマを決める
【終わりに】 最後 尻尾
何気ない本の1説が誰かに刺さることがある。
なんでも無い本の1ページによって人生が変わるという人もいる。
本の良し悪しは、読みてによって変わる。
変わらなければならないのは、読み手の方

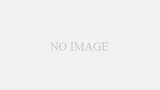
コメント